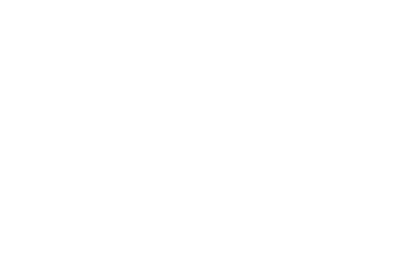- HOME>
- 糖尿病網膜症
糖尿病網膜症とは

糖尿病網膜症は、糖尿病が長く続くことで目の網膜に異常が起きる病気です。日本では成人の失明原因として最も多いもののひとつです。
網膜は目の奥にある薄い膜で、カメラでいうとフィルムのような役割をしています。ここに光が当たることで物を見ることができます。
糖尿病で血糖値が高い状態が続くと、網膜の細い血管がダメージを受けてきます。血管が詰まったり、形が変わったりして、網膜に十分な酸素や栄養が届かなくなります。
体はこの状態を改善しようとして新しい血管を作りますが、この新しい血管はとても弱く、簡単に破れて出血します。また、網膜を引っ張って剥がしてしまうこともあります。
糖尿病になってから数年、あるいは10年以上経ってから発症することが多いです。
糖尿病網膜症は、
初期には自覚症状がほとんどないため、定期的に眼科で検査を受けることがとても大切です。
糖尿病の基本
糖尿病は血液中の糖(ブドウ糖)が多くなる病気です。通常、食事をすると膵臓からインスリンというホルモンが出て、血糖値を調整します。しかし糖尿病ではこの仕組みがうまく働かず、血糖値が高いままになります。
高い血糖値は全身の血管に悪影響を与え、目だけでなく腎臓や神経など、体のさまざまな部分に合併症を引き起こします。
糖尿病網膜症の進行段階
糖尿病網膜症は進行具合によって3つの段階に分けられます。
単純糖尿病網膜症
初期の段階です。網膜の細い血管に小さな膨らみ(微小動脈瘤)ができたり、少量の出血が見られたりします。この時期はほとんど自覚症状がなく、眼科検査で発見されることがほとんどです。
前増殖糖尿病網膜症
病気が進行すると、網膜の血管がより広い範囲で詰まり始めます。網膜に酸素が足りない状態になり、より大きな出血や、綿のような白い斑点(綿花状白斑)が見られるようになります。血管の形も変わり、ビーズのように膨らんだり、くねくねと曲がったりします。
この段階でも自覚症状がないことが多いですが、視力が少し落ちることもあります。適切な治療を受けないと、さらに進行するリスクが高まります。
増殖糖尿病網膜症
最も進んだ段階です。酸素不足を補うために、網膜に新しい血管が作られます。しかしこの新しい血管はとても弱く、すぐに破れて出血します。また、血管と一緒に線維状の組織も増え、これが網膜を引っ張って剥がす(網膜剥離)こともあります。
この段階になるとこのような症状が現れることがあります
- 目の前に黒い点や糸くずのようなものが見える
- 急に視力が落ちる
- 視野の一部が見えなくなる
適切な治療を受けないと、失明することもあります。
糖尿病網膜症の治療
治療方法は病気の進み具合によって変わりますが、どの段階でも血糖値をしっかりコントロールすることが基本です。
網膜光凝固術(レーザー治療)
網膜にレーザーを当てて、小さなやけどを作る治療です。通院でおこなわれ、主に次のような効果があります。
- 網膜の酸素不足を改善する
- 新しい血管ができるのを防ぐ
- すでにできた新しい血管を小さくする
レーザー治療は特に前増殖期や増殖期の患者さまに効果的です。治療によって病気の進行を遅らせることはできますが、すでに傷ついた網膜を元に戻すことはできません。多くの場合、治療後の視力は変わらないか、少し落ちることもあります。治療は局所麻酔の目薬でおこなわれることが多く、痛みは少ないのが特徴です。
硝子体手術
このような症状の網膜症では、手術が必要になることがあります
- 出血が長く残っている
- 網膜が剥がれている
- 網膜の表面に異常な膜ができている
手術では、目に小さな穴を開けて、特殊な器具を使って出血や異常な組織を取り除き、剥がれた網膜を元の位置に戻します。これは高度な技術が必要な手術で、レーザー治療だけでは対応できない重症の場合におこなわれます。手術後の視力回復は、網膜の状態や手術前の視力によって変わります。
当院での検査について
糖尿病網膜症は徐々に進行し、かなり進んでも自覚症状がほとんどないことが特徴です。また、糖尿病自体も症状が分かりにくい病気です。
失明という最悪の事態を避けるためには、血糖値をしっかりコントロールし、内科と眼科の定期検診を続けることが大切です。これにより、網膜症の発症を防いだり、進行を遅らせたりすることができます。
精密眼底検査
目の内部は透明なので、光を当てることで奥の状態を見ることができます。通常の検査では瞳を広げませんが、よりくわしく調べるために、瞳孔を広げる目薬(散瞳薬)を使います。
検査中の痛みはなく、目薬がしみる程度です。ただし、瞳が広がった状態では近くのものが見えにくく、まぶしく感じます。元の状態に戻るまで5〜6時間ほどかかるため、検査の日は車の運転はお避けください。
検査の頻度の目安
| 網膜症がない方 | 1年に1回 |
|---|---|
| 単純網膜症の方 | 3〜6ヶ月に1回 |
| 前増殖網膜症の方 | 1〜2ヶ月に1回 |
| 増殖網膜症の方 | 2週間〜1ヶ月に1回 |
蛍光眼底撮影検査

腕の血管から特殊な色素を注射し、この色素が目の血管を流れる様子を撮影する検査です。
この検査によって、通常の検査では分からない血液の流れ方、炎症の有無、変性の範囲などのくわしい情報が得られます。診断や治療方針を決める上で、とても重要な検査です。
予防と日常生活での注意点
糖尿病網膜症を予防し、進行を抑えるためには次のようなことに気をつけてお過ごしください。
血糖値をコントロールする
内科医と相談しながら、食事や運動、薬を適切に管理しましょう。
血圧と脂質も管理する
高血圧や高脂血症も血管を傷つける原因になります。
定期的に眼科検診を受ける
糖尿病と診断されたら、症状がなくても眼科を受診しましょう。
禁煙する
喫煙は血管の状態を悪くします。
適度な運動を心がける
増殖網膜症の場合は、激しい運動や重いものを持ち上げると出血の危険があります。医師に相談しながら適切な運動をおこないましょう。
早期発見と適切な治療により、視力低下や失明のリスクを大きく減らすことができます。
気になることがあれば、お気軽にさわだ眼科・皮膚科にご相談ください。